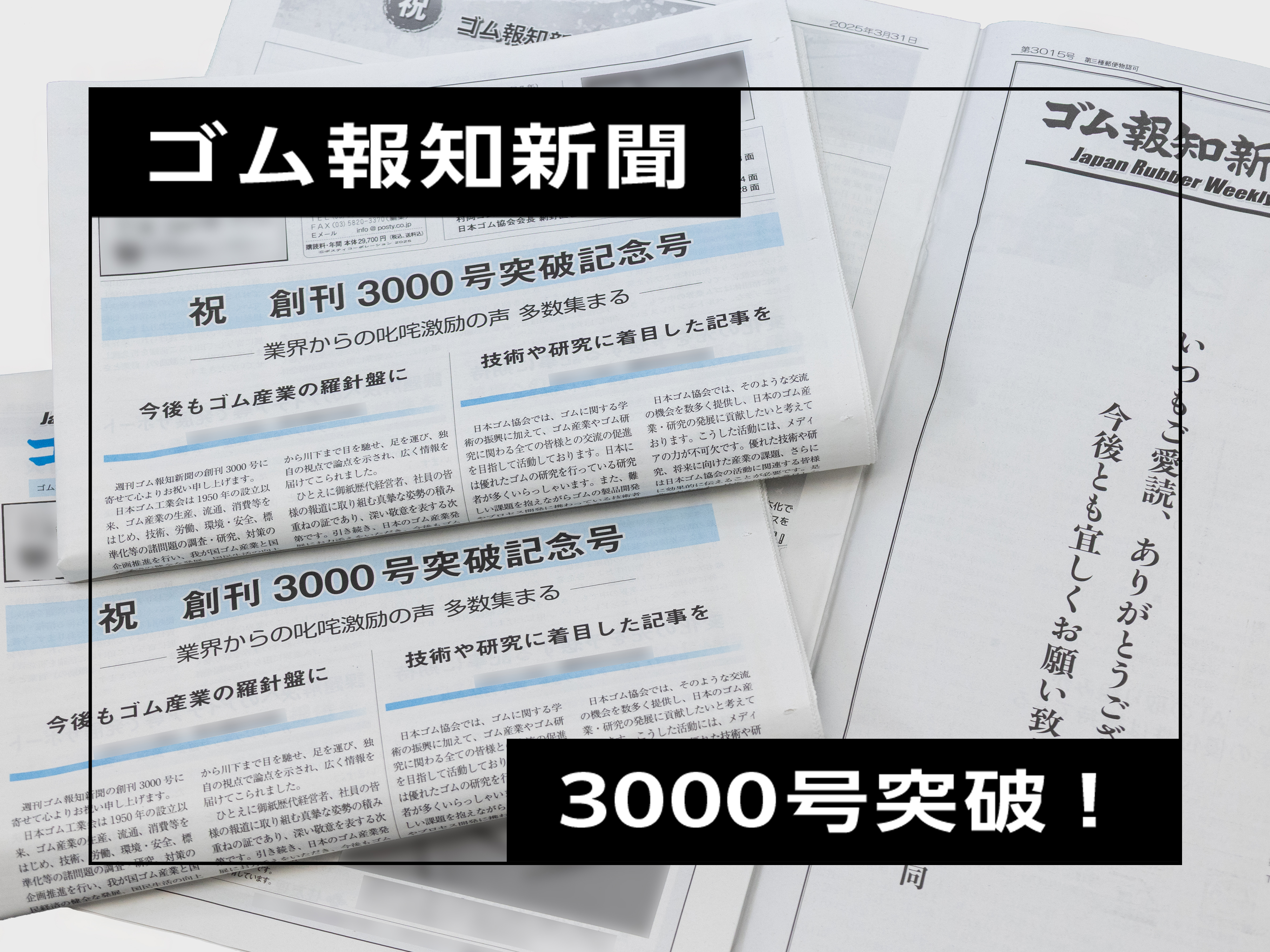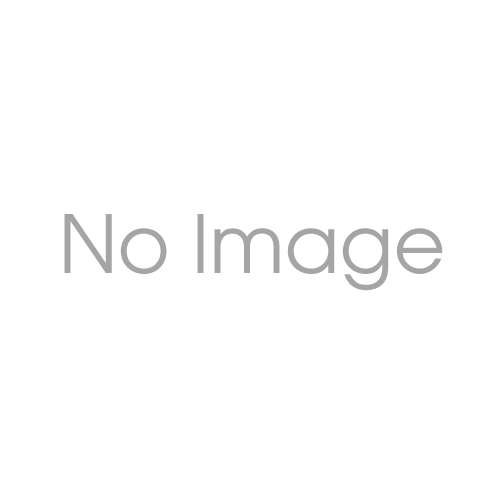
ゴムの最大の特長は、押されても、引っ張られても自分の力で元の姿に復元する「弾性」にあります。
この唯一無二といわれる特性から、タイヤをはじめ工業や電気・電子、医療、履物・スポーツ分野に使われ、工業材料として100年以上の歴史を持ちます。
しかし、ゴム特性のメカニズムの解明はいまだ完全に解き明かされていません。
そんな不思議な素材でもあるゴムには二種類――ゴムの樹といった植物由来の「天然ゴム」と、主に石油由来の「合成ゴム」――があります。
天然ゴムはタイヤに最も用いられます。一方、合成ゴムはタイヤだけでなく、耐熱や耐寒、耐油、耐候性といった特性を生かし工業用品用途にも幅広く使われています。
ここでは、合成ゴムについてご紹介します。

合成ゴムとは?
合成ゴムは、天然ゴムと同様に弾性を持つ高分子化合物です。
しかし植物由来の天然ゴムとは原料が異なり、石油などの化石燃料を原料として人工的に合成し製造されます。
その一般的な製造方法は、モノマーと呼ばれる小さな分子を化学反応によって結合させ、高分子を作り出すという方法です。
天然ゴムにはない優れた特性を持つものが多く、用途に合わせて様々な種類が開発されています。
合成ゴムと天然ゴムはなにが違う?
冒頭に書いた通り、ゴムには、①天然ゴムと②合成ゴムの二種類があります。
これらゴムの違いは原料にあります。天然ゴムは植物であるゴムの樹の樹液を原料として作られる一方、合成ゴムは主に石油由来の原料で作られます。
合成ゴム開発(誕生)の経緯
合成ゴムは歴史的には新しいものです。
20世紀に入ってから、世界規模で本格的に合成ゴムの開発が始まりました。
天然ゴムの産地に限りがあることから、アメリカやドイツがタイヤに使う天然ゴムの代替(類似品)として開発した経緯を持ちます。
また、天然ゴムは熱や油に弱いというデメリットもあります。それらデメリットを補うための機能が付与された合成ゴム開発も進んでいきました。
合成ゴムの強み(とデメリット)
合成ゴムは、天然ゴムにはない優れた特性を備えており、様々な分野で利用されています。
例えば天然ゴムよりも耐熱性や耐寒性に優れ、厳しい環境でも安定した品質を保つことができる種類があります。
しかし、全ての点で天然ゴムよりも優れているわけではありません。製品の原材料として用いる際は、それぞれの合成ゴムが持つ特性を理解し、用途に合わせて適切なゴムを選ぶことが重要となります。
主要な合成ゴムの種類
合成ゴムはモータリゼーションの発展によって種類が増えました。

用途に応じて2つのカテゴリーに分けることができます。①汎用合成ゴム②特殊合成ゴムです。
それぞれのカテゴリー内で代表的な合成ゴムを紹介します。
汎用合成ゴム(一般用ゴム)
主にタイヤに使用される合成ゴムを「汎用合成ゴム」と呼びます。代表的なものにスチレンブタジエンゴム(SBR)やブタジエンゴム(BR)、ポリイソプレンゴム(IR)があります。

スチレン・ブタジエンゴム(SBR)
合成ゴムとして、もっとも多量に生産、消費されています。スチレンとブタジエンの乳化重合、または溶液重合によって得られます。
そもそも重合反応とは、小さな分子(モノマー)がたくさん結合して、大きな分子(高分子)を作る化学反応のことを指します。
乳化重合とは、2種類以上のモノマーを水中に乳化させて重合する方法です。また溶液重合とは、モノマー(小さな分子)を溶媒に溶かして、重合する方法です。
主にタイヤや履物、ベルト、ホース、防振ゴムなどに使用されます。
ポリブタジエンゴム/ブタジエンゴム(BR)
天然ゴム、SBRの次に多く使用される合成ゴムです。ブタジエンの溶液重合によって得られます。
天然ゴムやSBRと比べて、耐摩耗性、反発弾性に優れる合成ゴムで、低温での特性変化が少なく、発熱性も低いものになります。
主にタイヤに使用されるほか、ゴルフボールの主素材でもあります。
ポリイソプレンゴム(IR)
分子構造が天然ゴムに最も近く、「合成天然ゴム」とも呼ばれる合成ゴムです。
工業的に製造されるため、天然ゴムに比べてゴミ等の不純物が少なく、均一な品質を有します。
タイヤのほか、医療用ゴム製品などに用いられます。
特殊合成ゴム
自動車のエンジン回りに使われるゴムや工業用品向けに使われるクロロプレンゴム(CR)やアクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、ブチルゴム(IIR)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)、エピクロルヒドリンゴム(ECO)、アクリルゴム(ACM)、シリコーンゴム(Q)、フッ素ゴム(FKM)などを「特殊合成ゴム」と呼んでいます。
クロロプレンゴム(CR)
歴史上最も早く開発された合成ゴムの一つです。
アセチレンまたはブタジエンを原料としたクロロプレンモノマーの乳化重合によって製造されます。
耐候性、耐オゾン性、耐熱老化性、耐油性、耐薬品性、難燃性などの環境抵抗性を一通り備えています。
自動車部品、一般工業用品、建材、接着剤など幅広い分野で用いられています。
アクリロニトリルブタジエンゴム/ニトリルゴム(NBR)
最も広く使用されている耐油性合成ゴムです。
ブタジエンとアクリロニトリルの乳化重合によって得られます。 ポリマー中に含まれるアクリロニトリル量が増えるにつれて耐油性は向上しますが、耐寒性は悪化します。
その特性である耐油性を生かし、燃料ホース、オイルシールといった燃料、オイル周りの製品に用いられます。
水素化ニトリルゴム(HNBR)
水素化ニトリルゴム(HNBR)は、ニトリルゴム(NBR)の二重結合を選択的に水素化させた合成ゴム。
NBRの優れた耐油性はそのままに、耐摩耗性、耐熱性、耐候性などが向上した高性能なゴム材料です。
エチレンプロピレンゴム(EPM、EPDM)
エチレンとプロピレンというモノマーを主成分とする合成ゴムです。
耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、自動車部品を中心に様々な産業で幅広く利用されています。耐候性の高さから、電線ケーブルなど屋外で長期的に使用される製品にも適しています。
ブチルゴム(IIR)
イソブチレンと少量のイソプレンを重合した合成ゴムです。
ガス透過率が極めて小さく、空気の透過率は天然ゴムの約10分の1と言われています。その優れた気密性のほか、電気絶縁性も良く、タイヤのインナーライナーや電線に用いられています。
また、反発弾性が低く、エネルギー吸収性に優れるため、振動吸収材にも使用されます。
クロロスルフォン化ポリエチレン(CSM)
ポリエチレンに塩素と硫黄を反応させてできる合成ゴムです。
耐候性、耐オゾン性、耐薬品性、耐熱性、明色安定性に優れています。
アクリルゴム(ACM)
アクリル酸エステルを主成分とする合成ゴムです。
フッ素ゴムやシリコーンゴムに次ぐ耐熱性に加え、耐候性、耐オゾン性にも優れます。各種潤滑油、燃料油に対しても優れた耐性を示します。
自動車部品の中でもエンジン回りで多く用いられます。
エピクロルヒドリンゴム(ECO)
エピクロルヒドリンのホモポリマー(CO)とエピクロルヒドリンとエチレンオキシドとの重合体(ECO)などがある合成ゴムです。
耐油性、耐オゾン性、低ガス透過性に優れ、半導電特性も有します。 自動車部品のほか、半導電特性を生かしプリンタローラにも用いられています。
多硫化ゴム(T)
二塩化エチレンなど多硫化ソーダとの縮合反応により得られる硫黄を主鎖に持つ特殊合成ゴムの一種。
加工に際して悪臭を発すること、加硫物の機械的性質が劣るなどの欠点を持つ一方で、耐油性や耐溶剤性、耐オゾン性、耐透過性などに優れています。
ウレタンゴム(U)
ポリエステルあるいはポリエーテルとイソシアナートとの反応によって得られるゴム状弾性体を総称してウレタンゴムと呼びます。
原料として使用するポリエステルやポリエーテルの種類、ジイソシアナートの種類、反応条件や架橋方法によって、特性が異なります。
引張強度や耐摩耗性、耐油性に優れる一方で、耐酸、耐アルカリ、耐水性に乏しく、耐熱性も比較的悪いという弱点があります。
シリコーンゴム(Q)
シロキサン結合という独特の基本骨格を有し、耐寒性、耐熱性に優れ、広い温度域でゴム弾性を示す合成ゴムです。電気絶縁性にも優れます。
電気、電子、自動車、食品、医療など幅広い産業で用いられています。
フッ素ゴム(FKM)
フッ素を含有するゴムの総称で、ゴムの中で最も優れた耐熱性を有するほか、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性などの特徴を持つ合成ゴムです。
主な用途は自動車部品ですが、化学プラントや半導体製造装置の部材等にも用いられています。高価な合成ゴムの一つです。
一方で、接着し難いという弱点もあります。
合成ゴムに関する動向
バイオマス由来の合成ゴム開発の推進
合成ゴムのモノマーであるブタジエンやイソプレンでは、石油由来ではなく、動植物由来の有機物を利用するバイオマス由来の開発が活発に進められています。
電気自動車(EV)化への対応
昨今は鈍化しているとも言われる電気自動車(EV)化ですが、EVの部品に合わせた合成ゴムの開発も進んでいます。
バッテリーやモーターなど、EV特有の部品に使用する合成ゴムの需要は、新たな市場を開拓するチャンスとなります。

中国の過剰生産への対応
鉄鋼や汎用樹脂等で世界的な問題となっている中国の過剰生産の影響が、合成ゴムにも広がっています。特にタイヤ向け合成ゴムの汎用品を中心に、中国の過剰生産の影響を受けています。
中でも、BRの状況が深刻です。BR自体の需要は世界的に堅調な推移をみせているものの、中国メーカーを中心とした需要を上回る生産能力の増強により、BRの市況が大きく低迷しています(2024年12月時点)。
なお、タイヤ向け合成ゴムの中でも特殊品にあたるS-SBR(溶液重合スチレンブタジエンゴム)などは過剰生産の状態にないとされています。
国内の生産能力が減少傾向に
合成ゴムは、国内の自動車生産などと共に拡大してきましたが、それら産業が地産地消のため海外進出したことで、国内需要が伸びていません。
さらに国内プラントの老朽化も進んでおり、生産を停止する国内メーカーも出てきています。国内の生産能力は減少傾向にあると言えます。
海外では中国を中心に新興国で巨大な合成ゴムプラントが建設されていますが、新たに国内の生産能力を拡大する路線で進む国内メーカーはいないのが現状です。
進む高付加価値化
中国の過剰生産やそれに伴う市況低迷などの背景も踏まえ、国内メーカーでは性能や品質などを武器に、それらの優位性が発揮できる用途やユーザーへの対応、高付加価値化の推進といった動きが中心になってきています。
もっと詳しく知りたい人はこちら
合成ゴムについてもっと詳しく知りたい方は、ポスティコーポレーションが発刊しているゴム年鑑ほか、当社の出版物をぜひチェックしてください。
ポスティコーポレーションは、タイヤや工業用品をはじめとする「ゴム業界」内外の情報発信を行う業界紙の会社です。
業界に関する情報を発信する週刊紙「週刊ゴム報知新聞」のほか、様々な専門書籍も発刊しています。

週刊ゴム報知新聞
ゴム産業・ゴム企業に関連するあらゆる情報と解説を掲載している業界新聞です。

ゴム年鑑
ゴム産業の現況を調査・分析し解説した、業界唯一の日本ゴム工業会推薦図書!
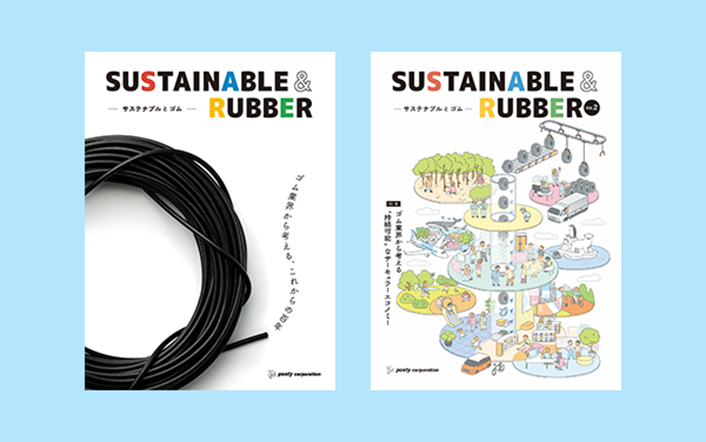
SUSTAINABLE & RUBBERシリーズ
ゴム・シューズ業界の持続可能な取り組みにフォーカスした書籍です。新入社員研修や学生の業界理解にもご活用いただけます。全ページオールカラーで、視覚的にも楽しく読み進められる誌面構成です。
サービスに関しては、こちらをご覧ください。